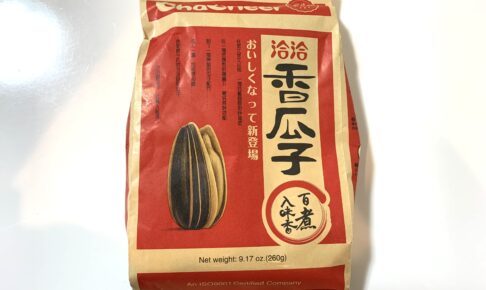中国のお菓子と言うと、皆さんはどんなものを思い浮かべるでしょうか。杏仁豆腐にマンゴープリン、天津甘栗も?!確かにどれも、中華街や中華料理店で見かける定番スイーツですね。でも、中国は広く歴史や文化がさまざまなので、私たちの知らない伝統菓子が他にも沢山あるんです!そこで今回は、本場中国の伝統菓子と、手に入るお店をご紹介します。
中国産伝統お菓子・スナック10選!
月餅(ユエビン)
中国の十五夜、中秋節のお月見に欠かせない伝統菓子で、日本では「げっぺい」と呼ばれています。中国全土で食されており、歴史は大変古く、唐の時代から食べられています。
一般的に知られているのは、薄い皮に、小豆・胡麻・ナッツ・ハスの実などの餡がぎっしり入れられたもので、中心に塩漬け卵黄が入り、皮の表面には細やかな装飾があります。その他、ひき肉やシーフード入りのしょっぱいもの、皮が茶色いもの、白いもの、カリカリのもの、モチモチのもの、平たいもの、球体のものなど、種類が多く地域によってさまざまで、広式、京式、蘇式、潮式、などの流派があります。
月餅が丸いのは月見をしながら一家団欒の意味があり、毎年この時期になると、お世話になった人に贈り合う習慣があります。日本で言うところの、お中元やお歳暮に近い感覚です。
麻花(マーファ)
中国北部、天津のお土産として有名な伝統的なお菓子です。まるで麻の糸を撚った状態に似ていることから、その名が付けられました。実はあまり知られていませんが、麻花はそうめんのルーツとも言われています。確かに、原料や撚り糸のような見た目も似ていますね。機織りが上達するようにとの願いを込めて、七夕の織姫へお供え物する行事食になりました。
小麦粉をこねて縄状にねじり、油で揚げて作られるので、味や食感は日本のかりんとうに似ています。甘さは控え目なのですが、とても硬く、噛めば噛むほど小麦の風味が口いっぱいに広がります。日本には江戸時代に伝わり、現代でも長崎中華街では、「よりより」や「唐人巻 (とうじんまき)」の愛称で親しまれています。
ドライフルーツ
東洋医学的観点から、中国の方にとって、ドライフルーツは医食同源を叶える立派な健康スナックです。代表的なのは、サンザシ、なつめ、クコの実などで、お茶請けから薬膳料理にまで、日常的に幅広く食べられています。
中国には「一日3粒のなつめを食べると永遠に年をとらない」ということわざがあるほど、なつめはアンチエイジングに高い効果があると期待されています。また、クコの実は別名ゴジベリーと呼ばれ、こちらも老化防止や疲労回復の効果がハリウッドセレブに人気のスーパーフードです。ドライフルーツや漬物、シロップにして保存したサンザシは、胃腸の具合がすぐれない時に食すと良いと言われ、おやつとしてだけででなく、漢方食の感覚で食べるのだとか。中国の方は、食べ物による身体への影響について日頃から意識する習慣があるようです。
瓜子(グアズ)
瓜子とは瓜科の植物の種の総称で、具体的には、ひまわりの種やスイカの種、かぼちゃの種のことを指します。種を殻ごと煎って、調味料で味付けした状態で売られており、殻を割って中身だけを食べます。中国の方は子供からお年寄りまでみんな瓜子が大好き!お茶請け、来客時、口が寂しい時、どんなシーンでもポリポリ食べています。道端やバス停、電車内やスタジアムなんかにも、あちこちに大量の殻が落ちていることに、外国人はびっくりすることでしょう。瓜子の歴史は古く、紀元前から食されていた事が分かっています。栄養価が高く、カリウム・カルシウム・マグネシウム・ビタミンが豊富で健康に良い事を、当時の人は経験的に知っていたのかも知れません。筆者がハマったのはキャラメル味のひまわりの種!殻を剥くのに少々コツが要りますが、一度食べ出すと止まらなくなるほどクセになります。
糖葫芦(タンフール)
串刺しのサンザシに飴をかけた、中国北部の伝統菓子です。12世紀、中国の南宋時代が起源の薬膳デザートで、当時病気の王女がこれを食べ、見事回復を遂げたとされています。現在は中国北部の冬の名物として知られており、露店で売られているものが一般的ですが、スーパーなどでは冷凍の糖葫芦も売っています。
酸味のあるフレッシュなサンザシに甘くパリパリの飴がけが、日本のりんご飴と似ており、見た目の可愛さからも、特に女性や子供に人気のあるデザートです。
日本では中国物産展で冷凍コーナーで手に入るので、是非試してみてくださいね!
沙其馬・沙琪瑪(サチマ・シャーチーマー)
小麦粉と卵、膨らし粉を混ぜた生地を油で揚げ、飴で固めた、日本のおこしに似た中華菓子です。清の時代に満州族によって作られ、今では中国全土と香港・台湾のどのお店でも見られるほどに広まり、中華圏の定番スナックとなりました。
甘さ控えめでふんわり柔らかく軽く、サクサクの生地と蜜のしっとり食感が特徴です。
黒糖味、レーズン入り、胡麻風味などアレンジされたフレーバーもあり、老若男女に支持されています。カロリー高いことから朝食代わりにつまむ人もいるのだそうです。
湯円・湯圓(タンユェン)
冬至や春節に食べる風習がある、冬の暖かいお菓子です。日本の白玉団子に良く似ていますが、餡入りなのが特徴です。
ピンポン玉サイズのまん丸い団子は、元宵節(げんしょうせつ)の満月に見立てられており、また湯円の発音が一家団らんを意味する言葉の発音と似ていることから、家族の幸福を願う縁起物として、元宵節の朝に家族みんなで頂く風習があります。
モチモチ、つるつるのお団子の中には、黒ゴマ、ピーナッツ、五目ナッツなどのトロリとした甘い餡が入っており、お湯に入れて提供されるので冷めずに暖かいまま食べることができます。白い団子の他、もちあわや紅芋入りのカラフルな湯円もあり、見た目にも楽しい、冬の風物詩となっています。
寿桃包(ショウタオバオ)
桃源郷のお話にもあるように、中国では昔から、桃は仙果と呼ばれ、邪気を祓う魔除けの力や、不老長寿を叶える力がある幸運の果実と信じられてきました。
そのため、高齢者のお誕生日や、結婚式の祝いの席では必ず、桃を模した点心「寿桃包」を縁起物として食べる風習があります。
小麦粉で作った皮で餡を包み、桃に見立てて蒸しあげた点心で、中身の餡は黒餡、ハスの実餡、黄身餡などがあります。
芝麻球(チーマーチュウ)
中華街でよく見かける、揚げた胡麻団子の事で、中国では芝麻球と呼ばれています。
白玉粉のお餅の中に、小豆餡に黒ゴマとゴマ油を混ぜた餡を入れ、丸めた表面に白ゴマまたは黒ゴマをまんべんなくまぶし、油で揚げて作られます。
表面はカリッ、中はモチっとしており、ゴマの香ばしさと甘く滑らかな餡のコンビネーションが抜群に美味しいので、日本でも人気の中華スイーツです。
八宝粥

中国では、お釈迦様が悟りを開いたと言われる12月8日の臘八節(ろうはちせつ)の日に八宝粥を食べる習慣があります。複数の雑穀と豆やナッツをふんだんに使い、お砂糖を加え煮込んだ甘いスイーツタイプのお粥で、日本のぜんざいやお汁粉に似ています。
冷やしても温めても美味しく、カロリーが低いのに栄養価が高く消化に良いので、健康食品として人気を集めています。缶入りの八宝粥が売られており、手軽に食べれるため、日常的にも食べられるようになりました。中国でお粥と言えば朝ごはんのイメージですが、甘い八宝粥は小腹が減った時におやつ感覚で食べるのだそうです。
八宝粥という名前から、8種類の具が入っていそうと思われがちですが、必ずしも8種ではなく、沢山の種類という意味合いです。
中国伝統菓子・スナックが買えるお店
中国伝統菓子を紹介してきました。気になるお菓子はありましたか?実は、これまでに紹介したお菓子はどれも日本で買うことができます。皆さんの近所の中国物産展でも見つけられるものがあると思いますが、ここでは代表的なお店をいくつかご紹介します。
KOKYO MARKET
国内最大級のアジア輸入食品・お酒専門ネットスーパーです。
中国や台湾のスナックも多く取り扱っています。
特徴はなんといっても、「全品送料無料」。お試し買いができちゃいます
華僑服務社
東京の小アジア、新大久保にある、大型アジア食品スーパーです。お菓子類だけでなく、調味料や冷凍食品など、品揃えが大変充実しているので、見ているだけでもお買い物が楽しくなりますよ。遠方の方は、同社が運営するネット通販、「アジアンストア」の利用がおススメです。
スペシャル・チャイナ
本家公式通販ページは中国語のみの、中国の方向けの中華食材専門店です。
楽天店は日本語表記になっており、季節ごとの特集ページなどがあって見やすい構成になっていますよ。3900円以上のお買い物で送料無料なので、利用しやすいところも◎
まとめ
いかがでしたか?季節行事や医食同源の考えから生まれたものなど、中国菓子にはその歴史と文化を感じられて、とても興味深いものがあります。餡やお餅など、和菓子に近いことで親しみを持って食べられるものも多いですし、行事に合わせて食べるのもまた風情がありますね。日本でも簡単に入手できますので、ぜひ試してみてください。