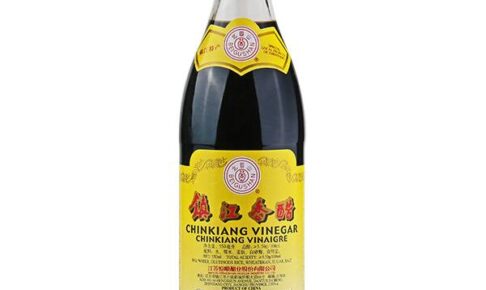街中で見かける中国食材のお店。どんなものを売っているのか興味はあるけれど、何だか入りづらい…と思う人も少なくないはず。そこで今回は、中国ネイティブ達が実際に買っている厳選食品を、ランキングで一挙ご紹介いたします!中国語の読み方も載せていますので、覚えておくと自慢できるかも?
おススメ中国食材 ドリンク部門
1, 王老吉(ワンラオジー)
王老吉は、中国で最も多く飲まれている国民的ドリンクで、スーパー、売店など、中国で売っていない場所はないと言われるほどポピュラーな商品です。様々な漢方成分が配合され、お砂糖で飲みやすくしたハーブティーで、身体の熱を放出する効果があるとされています。火鍋のお供や体調不良時に良く飲まれ、老若男女に愛されて続けています。
2, 旺仔牛乃(ワンチャイ牛乳)
キャッチーなパッケージが特徴のこちらの飲料は、中国人なら誰もが子供の頃に飲んだことがあるという、ロングセラー商品の練乳ミルクです。とっても甘いので、冷やしてすっきりと飲むほか、冬にホットミルクにして飲むのもいいですね。缶入りなので賞味期限が長く、ストックしておけるのも◎一度飲むとハマる味です。
3, 椰樹牌椰汁(イェーシューパイイェージー)ココナッツジュース)
中国南部、海南島の特産品のココナッツで作られた、ココナッツジュースです。中国では30年以上愛されるベストセラー商品で、どこのスーパーにも必ず売っている定番商品です。独特のデザインのお陰で一度見たら忘れられないほどのインパクトですが、お味は優しく、甘さすっきり。冷やしても温めても美味しく飲めます。
4, 酸梅湯(サンメイタン)

梅・サンザシ・陳皮などの入った、甘酸っぱい薬膳ドリンクです。梅の実を燻して作られるので、スモーキーな香りが特徴的。疲労回復、夏バテ予防、消化促進などの効能があるとされ、夏の定番ドリンクとなっています。漢方材料を煮だしたシロップを、水割り、お湯割り、ソーダ割りにするのが一般的ですが、ペットボトル商品が一番手軽に試せるので人気があります。
5, 冰糖雪梨(ビンタンシュエリー)なしジュース
冰糖雪梨は、梨を甘く煮た中国の伝統的な薬膳スイーツのこと。肺や喉を潤し、喉のイガイガや咳止めに効果があると言われています。こちらの商品はそのスイーツと同じ名前で、手軽に飲めるジュース盤といったところでしょうか。美味しく体調を整えられるので、季節の変わり目や、乾燥する時期の不調にもってこいです。
おススメ中国食材 調味料部門
1, 十三香粉(シーサンシャンフェン)
その名の通り、13種類のスパイスをブレンドした、伝統的な調味料です。辛みはなく、主に肉の臭み消しなどに使用されます。一振り入れるだけで、鼻から抜ける香りはまさに本格中華!これで味付けしたルーローハンは絶品に仕上がりますよ!似た商品に五香粉がありますが、十三香粉の方がより複雑で豊かな香りがします。
2, 花椒(ホアジャオ)
別名、中国山椒とも呼ばれ、日本山椒とは違う種類のスパイスです。爽やかな香りと、痺れる辛さが特徴的で、麻婆豆腐に使われるのが代表的。その刺激的なフレーバーに魅せられた人が続出し、マー活という言葉が生まれたほどです。ホールとパウダーの2タイプがあり、炒め物や煮込みにはホール、下味やタレづくり、トッピングにはパウダーが適しており、用途に合わせて形状を選ぶと良いです。
3, 老干媽(ラオガンマー)
中国のどこの家庭にも置いてある必需品!中国最大の老干媽というブランドの、中国版食べるラー油です。炒め物や餃子のつけダレ、ラーメンのトッピングなど、何にでも使え、何でも美味しくなるという、大変優秀な調味料です。肉入りやピーナッツ入り、豆鼓入りなどさまざまな種類があるので、好みや特徴ごとに使い分けるのが本場流。
4, 豆豉(トウチ)
黒豆に塩を加え発酵させて作る、中華に欠かせない調味料です。味噌や醤油のような旨味とコクをを出し、料理に深みを加えてくれます。そのままでは乾燥していて塩辛いので、少量の水を加えて柔らかくし、刻んで油と炒めると、その風味を最大限に引き出すことができます。麻婆豆腐、回鍋肉をはじめ、魚介や野菜の炒め物に入れると、いつもの中華が本格的になりますよ!
5, 鎮江香醋(ジェンジアンシアンツー)
鎮江香酢とは、中国の黒酢のことで、中国江蘇省鎮江市の香りの良いお酢、という意味です。日本の黒酢と違い、ツンとした刺激臭がなくまろやかで、アミノ酸の濃厚な旨味とコク深い風味が特徴です。ほのかな甘味と塩味があるので、老干媽ラー油と1:1で合わせるだけで万能の点心つけダレに!酢豚、煮込み料理にも◎香酢を取り入れることで、便秘や
高血圧改善、疲労回復の効果も期待できます。
おススメ中国食材 お菓子部門
1, 瓜子(グアズ)
瓜科の植物の種のことで、ひまわりの種やスイカの種、かぼちゃの種をこう呼びます。その中でも、一番人気はひまわりの種!一度食べ始めると止まらなくなり、あっという間に手元が殻だらけに…というのが中国あるあるです。塩味や甘いもの、スパイシーなものまで、さまざまなフレーバーの商品があり、おやつやおつまみに最適です。
2, 麻花(マーファ)
小麦粉を練って縄状にねじり、油で揚げたお菓子で、撚った麻の糸に形状が似ていることが名前の由来です。甘さは控え目でとても硬く、噛めば噛むほどに香ばしい小麦の風味が広がります。日本のかりんとうに似ており、実は江戸時代には既に日本に伝わっていたそうです。長崎の中華街では、「よりより」という名称で販売され、お土産の定番として人気なのだそう。
3, 月餅(ユエビン)
日本でもお馴染みの月餅(げっぺい)は、中秋節のお月見に欠かせない伝統菓子で、唐の時代から食べられているのだそうです。お世話になった方へ贈りあう風習があり、各店からさまざまな種類の月餅が販売されるので、十五夜近くになると人気店には行列ができるほど。胡麻餡や小豆餡、ハスの実餡に塩漬け卵黄入りなど、中身の種類も豊富で迷ってしまいます。
4, 沙其馬(サチマ)
小麦粉と卵を練った生地を細かく切って油で揚げ、蜜をかけて固めた後に四角く成形した、ふんわりサクサク食感のお菓子です。製法や見た目が日本のおこしによく似ていますが、さらに甘さ控え目で、軽やかで柔らかく、素材の味を味わうことができます。プレーンのほか、胡麻味やレーズン入りなどもあります。
5, 湯円(タンユェン)
湯「ゆ」に円「まる」と書いて湯円(タンユェン)と読みます。その字の通り、お湯の中にまんまるのお餅が浮いている冬の定番デザートで、中国では大変ポピュラーです。お餅の中には甘くてトロトロのあんが入っており、日本の白玉の中にあんが入ったようなイメージ。湯円には複数種類があり、白い餅のほか、黒米やアワ、紫芋入りのカラフルなお餅があります。あんには、黒ゴマ、ピーナッツ、小豆などがあり、嬉しいバリエーションですね。冷凍のまま茹でるだけで出来上がるのでとっても簡単♪
おススメ中国食材 加工食品部門
1, 粽子(ツォンズ) 中華ちまき
粽(ちまき)は紀元前ら食べられている、端午節に欠かせない料理です。肉や卵黄入りのしょっぱいもの、小豆やナツメ入りの甘いものなど、豊富な種類からセレクトできます。複雑な工程のため、工場でも職人が一つ一つ手作りで笹の葉に包んでいるんですよ!真空パックの商品が多く売られており、蒸す、茹でる、レンチンで調理可能ですが、蒸すのが一番美味しくモチモチ食感を楽しめます。
2, 三鮮水餃子(サンセンジャオズ)
三鮮とは3つの具材の意味で、肉、野菜、海鮮を指します。ニラ、エビ、豚肉(卵が入る場合もある)で作られた餡を厚めの皮で包んだ、さまざまな具材の味わいと皮のつるモチ食感を堪能できる、水餃子の完成形とも言うべき一品です。茹でたてに、老干媽と香酢を混ぜたつけダレを添えるだけで、何個でも食べれる美味しさ!煮崩れしにくいので、スープや鍋の具にも適しています。
3, 海底撈(ハイディラオ)火鍋の素
海底撈は中国でとても有名な火鍋専門のチェーン店です。最近日本にも上陸し、待ち時間に施術を受けられるネイルサロンを併設するなど、ユニークなサービスが話題になりました。人気の火鍋を家庭でも食べられるようにと開発された火鍋スープの素を利用すれば、自宅で好みの具材の火鍋パーティーができますよ。一番人気は麻辣味、辛いのが苦手な人にはトマト味やキノコ味をどうぞ!
4, 鹹蛋(シエンタン)
鹹蛋はアヒルの塩漬け卵のことで、ピータンと並ぶ中華圏の発酵卵製品です。本場ではお粥のトッピングや、刻んで炒め物に入れたりと、調味料として使もわれ、家庭に欠かせない保存食品です。白飯との相性も抜群なので、ビギナーの方はまずその味を試してみて下さい。白身はそのままだとかなり塩気が強いのでちびちびと、黄身は濃厚な旨味がクセになります。
5, 紅焼牛肉麺(ホンシャオニュウロウメン)
世界一即席麺を食べる中国で、一番のシェアを誇る康師傅(カンシーフー)の看板商品がこの紅焼牛肉麺です。日本の日清カップヌードル的ポジションの国民食と言っても過言ではありません。醬油ベースに豆板醤の辛みを効かせ、八角や花椒の風味をまとった牛骨スープは、あっさりした中にも旨味とコクがあり、最後まで胃もたれせず食べれてしまいます。
まとめ
いかがでしたか?
中国ネイティブが物産店で本気買いしている食品を、部門別ランキング形式でご紹介しました。
初めて挑戦するものはハードルが高い、と思う方も多いと思いますが、私自身は比較的どれも日本人の口に合うものだと感じました。物産店で何を買うべきか迷っているとしたら、この記事で見たものを買えばほぼ間違いありません。その一歩が今後の選択肢を広げてくれます。まだ経験していない方はぜひ、本格中華にチャレンジしてみて下さいね!